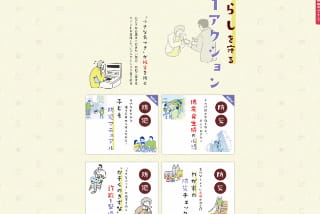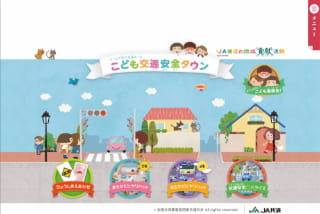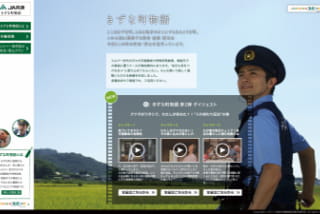-
交通安全対策NEWS2 アクセルとブレーキの
「踏み間違い」の危険性全国で毎日10件ほど発生している、アクセルとブレーキの踏み間違い事故。死亡事故は、75歳未満と比べて、75歳以上では13倍も高くなってきます。踏み間違いが起こる理由や、未然に防止するためのポイントなどをわかりやすくご紹介します。

アクセルとブレーキの「踏み間違い」の危険性や防止策について、
ポイントをまとめたダイジェスト動画やパンフレットをダウンロードいただけます。 -
交通安全対策NEWS1 高速道路における
「逆走」の危険性全国で2日に1件発生している高速道路の逆走。特に全体の7割が65歳以上の高齢者となっています。逆走が発生しやすい状況や未然に防ぐポイント、対処法などをわかりやすくご紹介します。

高速道路における逆走の危険性や対処法について、
ポイントをまとめたダイジェスト動画やパンフレットをダウンロードいただけます。
高齢ドライバー向け
交通安全対策NEWS
高齢ドライバーによる交通事故、「自分だけは大丈夫」と思っていませんか? 誰にでも起こりえるミスを防ぐためのポイントやいざという時の対処法、そして安全運転に関する最新情報などを映像や冊子で分かりやすくご紹介します。